|
|||||||||||||||||||||||||||||
日曜日はもちろん平日にも行列ができほどの人気で一度や二度見てもストーリーがわからない映画としても有名でした。この映画を見た観客は二通りのタイプに分かれるといわれていて、一つはピートの客で画面を食い入るようにみ、今日こそは何とかモノにしてやる(~Q~;)というタイプ、もう一つは話題の映画だから話の種に見ておこうか、本来SF系映画にはあまり興味のない人で少し見て「こらあかんわと(。_゜)?zzz寝てしまうか帰ってしまう2通りのタイプ。私も一度ではまったく理解できませんでした(・'・;)。それから十数年かたったある日、古本屋で【アーサーCクラーク博士著2001年宇宙の旅】文庫を発見!「ぉおーこの本はあのわけのわからん映画の本じゃ〜わと購入\100円(^^;読んでるあいだ前に見た映画シーンの一つ一つが鮮明によみがえり「ここ(・'・;)このシーンじゃ〜おーそうだったのか!ぉおー(~Q~;)感動と発見の連続、あとで二度三度とビデオを見直し、そしてまた原作を読みなおし・・おーやっぱしそうだったかー(〜Q〜;)と数十年ぶりに映画鑑賞を完結したのでありました(笑)。普通映画の作成には先に原作がありそれを元に映画化するものですが、この作品はアーサーCクラーク博士著の1950年「前哨」という短編小説を元に、2001年宇宙の旅の小説と映画が同時進行で書かれたため、原作が映画を上映する前に目に触れることがなかったこと、製作中も(ストーリー)を伏せて作られ映画の構成も言葉に頼らないものだった為(極端にせりふが少ない)映画を見ただけではストーリーがわからないように、作られていたのです。リピート客も考慮に入れて作られていたのではないかと思われます。この作品の正しい見かたはまず映画をみてそれから小説を読み、またその一つ一つのシーンの確認のためビデオを見てまた原作を読むですね(^^;!。 今までに見た純粋なSF映画のなかで、未だかつてこの作品にまさるものを見たことがありません。この作品が封切られた頃まだアポロが月に行く前にだったことを考えて見ても、いかに素晴で科学的にも裏付けのあるすばらしい作品だったことがおわかりになると思います。欧米でも日本でも数十年ロングランを続けた劇場もあると聞きます、またローマ法王もこの映画をご覧になって絶賛されたそうです。 (^^;今年がその2001年なわけで、でこの映画にいくらか興味があっても本まで買って読むのもなんだなーって人に、十分の一程度のダイジェストにしました(^^;後半はまだ整理できてないまま載せていますのであしからず。 |
||||
 最後に倉田わたるの2001年宇宙の旅の真相もお読みになってみてください。 最後に倉田わたるの2001年宇宙の旅の真相もお読みになってみてください。 |
||||
|
原初の夜 《絶滅への道》 |
|||||||
ヒトの進化 新しい動物が地上を闊歩しはじめた、多くの強大な生物の滅亡を見たこの世界では、その運命は秤の上を微妙に揺れ動いている状態だった、透明な石板がアフリカにおりて10万年のちもヒトザルはなにも発明していなかった。しかし彼らは変貌をはじめている、ほかの動物にはない技術も持つようになった。骨の棍棒は長くなり彼らはいっそう強くなった。やがて世界は変わり始めた20万年の間隔をおいて4つの巨大な波となって、氷河期が襲い、生物をふるいわけていき彼らは生き残った、違う形に生まれ変わっていたのだ。道具そのものが道具を作った者を作り変えたのである。最初の真の人間は道具や武器の点では百万年前と大した進歩はしてなかった、だが何にもまして重要な道具話すことを覚えたのである。 |
|||||||
|
TMA1 《特別飛行》 |
|||||||
|
|
スペースポッドは直径9フィートの球体で、推進の加速は月面上空に浮かぶくらいの力で窓のすぐ下には関節を持った2対の脚が突き出している。プールはスペースポットに乗り込むと注意深く制御装置・・小型計器パネルの最終チェックをした「外ドアを開けよ・ポッド離船はじめ」ジェットを半秒噴射させるとどれ自身の軌道をゆく独立した天体となった。長距離用のアンテナにたどりつくと、細心の注意で状況の観察をした。プールは背後から接近した、ポッドはスポットライトをつけディスカバリーの影を消すとようやく目的の装置が目に入った、AE35ユニットは4っつのナットでとめられた金属版の中にある、面倒な仕事でもなさそうだがポットの中からでは無理な作業だ。ポッドをアンテナから2フィート離して止め宇宙服に異常がないことを確かめ、ポッドの空気を排出した。ディスカバリーの外壁の手がかりをつかむと、袋から予備のAE35ユニットを取り出した。「これから装置をはずす、アンテナシステムのパワーを切ってくれ」「パワーを切った」ハルが答えた「ようし今装置を引っ張り出している」板は簡単にスロットから抜けた一分足らずで予備がその部分に収まった。パワーが回復するとき、アンテナが異常な回転をする場合を考えてゆっくりと離れた。「コントロールパワーを戻してくれ」ハル「パワーを入れた」 診 断 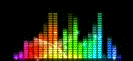 2人はメリーゴーランドの小さな作業場兼実験室に立っていた、AE35ユニット200%の過負荷をかけても故障予報は出ない、完全にテストをパスした。「ハルの故障予備装置が故障したってこは考えられるな」「危険はおかせない、このAE35ユニットはNGとして廃物庫の中に捨てよう、悩み事は帰ったあとでほかの連中に押し付ければいい」だが悩み事は地球からの次の送信ではじまった。「Xデルタ1・こちら管制室、2155号送信について、アルファーエコー35ユニット故障がないという報告はこちらの検査とも一致した、こちらのコンピューターを2台使ってさらにテストををおこなう結果が出たらすぐに知らせる・・・・・・・・」そのときの当直はフランク・プールだった、ハルから話はないのかと黙って待っていたがハルからの話はなかった。ポールマンはもう起きていてコピーを注いでいた。プールは不安を隠しきれない声でプールにおはようと言った、どうだい・・・「うん・・・」プールはゆっくり答えた「管制室からちょっとした爆弾宣言がでたよ、今のままでも危険はないが地球管制室に臨時に切り替える案を検討中だそうだ、プログラム分析のためにね」ハルがこの会話を聞いている一言あまさず聞いていることを2人はしっていた。 2人はメリーゴーランドの小さな作業場兼実験室に立っていた、AE35ユニット200%の過負荷をかけても故障予報は出ない、完全にテストをパスした。「ハルの故障予備装置が故障したってこは考えられるな」「危険はおかせない、このAE35ユニットはNGとして廃物庫の中に捨てよう、悩み事は帰ったあとでほかの連中に押し付ければいい」だが悩み事は地球からの次の送信ではじまった。「Xデルタ1・こちら管制室、2155号送信について、アルファーエコー35ユニット故障がないという報告はこちらの検査とも一致した、こちらのコンピューターを2台使ってさらにテストををおこなう結果が出たらすぐに知らせる・・・・・・・・」そのときの当直はフランク・プールだった、ハルから話はないのかと黙って待っていたがハルからの話はなかった。ポールマンはもう起きていてコピーを注いでいた。プールは不安を隠しきれない声でプールにおはようと言った、どうだい・・・「うん・・・」プールはゆっくり答えた「管制室からちょっとした爆弾宣言がでたよ、今のままでも危険はないが地球管制室に臨時に切り替える案を検討中だそうだ、プログラム分析のためにね」ハルがこの会話を聞いている一言あまさず聞いていることを2人はしっていた。
絶たれた回線 このごろではハルが予定にない発言をするとき、あらかじめわかるようになっていた。この数週間にいつのまにか彼についた癖で電子的咳払いがはいるのである、「ああ・・・・デーブ、君に報告することがある」「なんだ?」「AE35ユニットがまたおかしい」「わからんな、ハル2日で2つとも装置が駄目になってしまうことがあるかい」「不思議に思うかもしれないが、もうじき故障を起こすのは確かだ、デーブ」「故障の原因はなにだ」ハルはめずらしく長い間をおいて答えた「はっきりとはわからないな、デーブ前にいったとおりで、異常の正確な位置がつかめない」「とにかく管制室に報告してアドバイスを聞こう」と彼は問いをおいた、だが返事はなかった。地球からの連絡は通話回線とテレタイプによる通信で充分なのに、わざわざラジオ周波数帯で画像を送ってきたのは異例のことだった。プルーとボーマンは問題のこじれてきたことに気がついた「AE35ユニットの分析が終わった、故障はAE35ユニットにあるのではない・・解決策はそちらの9000を切り離して、地球管制方式に切り替える・・の交信中・突然管制官の声が消えたと同時に警報が鳴り響いた・非常事態!非常事態!「どうした?」ハル「予報したとおりAE35ユニットが故障した」「照準ディスプレイを見せてくれ」十字線から地球が外れはじめていた。「ちくしょうめ」ボーマンがいった。「ハルは正しかったわけだな」「あやまったほうがいい」「その必要はないよ」ハルが割り込んできた。「故障を喜んでいるわけではないが、私に対する信頼が戻ってくれればうれしい」「誤解して悪かった」ボーマンがいった。「それはそれとしてアンテナの手動コントロールをこちらに回してくれないか」「いま切り替えた」大変な努力は払ってアンテナを十字の方向地球に収めるのに成功した。 土星一番乗り  作業はその前にやったことの繰り返しだった・・しかしフランクは何一つおろそかにしなかった彼は再びベティーをアンテナ支柱の基部から20フィートばかりのところに止め、ポットのコントロールはハルに切り換えてドアをあけた。「これから外に出る」彼はボーマンに報告した「すべて異常なし」コントロールデッキのボーマンにlうなり声とあえぎが聞こえてきた。「ナットの一つが動かない強く締めすぎたらしい--フィーやっとはずれた」「ハル-------ポットのライトを20度右に回してくれ・・・ありがとう・・・それでいい・・・」何かおかしい意識のはるかな奥で、かすかに警告が鳴り響いた、数秒間考えをめぐらした後、彼はやっと原因が思いあたった、ハルは命令を実行したが今までと違って、了解の合図を送らなかったのだ。アンテナの台座にいたプールは、作業に忙しく異常に気がつかなかった、動くはずのないところで何かが動いた!、驚いて目をあげた。スペースポットのスポットライトがいま彼の周囲で動きはじめているのだった。繋ぎとめるときへまをしたのかもしれない。だが次に来た驚きは、恐怖の入り込む余地のないほど大きなものだった、スペースポットが最大推進力でプールを押しつぶしプールの命綱を引っ掛けたまま星の世界に全速力で加速しながら飛び去っていった。ボードマン彼は叫んだ「ハルどうしたんだ?ベティーの逆噴射を最大のしろ!逆噴射だ!」かれは叫んだ「フランク・・フランク聞こえるか・・聞こえたら手を振ってくれ」その時だった彼のの声に答えるようにプールが手を振った、つかの間ポーマンは首筋の毛がが逆立つのを感じた、突然唇が乾いた、生きているはずの無いプールが手を振ったのだ。五分後ポッドとその連れは星の中に消えていた、ボーマンは長い間空虚に目をこらし、一つの考えだけが鳴り響いていた・・フランクプールは土星に一番乗りする人間になるだろう・・・。 作業はその前にやったことの繰り返しだった・・しかしフランクは何一つおろそかにしなかった彼は再びベティーをアンテナ支柱の基部から20フィートばかりのところに止め、ポットのコントロールはハルに切り換えてドアをあけた。「これから外に出る」彼はボーマンに報告した「すべて異常なし」コントロールデッキのボーマンにlうなり声とあえぎが聞こえてきた。「ナットの一つが動かない強く締めすぎたらしい--フィーやっとはずれた」「ハル-------ポットのライトを20度右に回してくれ・・・ありがとう・・・それでいい・・・」何かおかしい意識のはるかな奥で、かすかに警告が鳴り響いた、数秒間考えをめぐらした後、彼はやっと原因が思いあたった、ハルは命令を実行したが今までと違って、了解の合図を送らなかったのだ。アンテナの台座にいたプールは、作業に忙しく異常に気がつかなかった、動くはずのないところで何かが動いた!、驚いて目をあげた。スペースポットのスポットライトがいま彼の周囲で動きはじめているのだった。繋ぎとめるときへまをしたのかもしれない。だが次に来た驚きは、恐怖の入り込む余地のないほど大きなものだった、スペースポットが最大推進力でプールを押しつぶしプールの命綱を引っ掛けたまま星の世界に全速力で加速しながら飛び去っていった。ボードマン彼は叫んだ「ハルどうしたんだ?ベティーの逆噴射を最大のしろ!逆噴射だ!」かれは叫んだ「フランク・・フランク聞こえるか・・聞こえたら手を振ってくれ」その時だった彼のの声に答えるようにプールが手を振った、つかの間ポーマンは首筋の毛がが逆立つのを感じた、突然唇が乾いた、生きているはずの無いプールが手を振ったのだ。五分後ポッドとその連れは星の中に消えていた、ボーマンは長い間空虚に目をこらし、一つの考えだけが鳴り響いていた・・フランクプールは土星に一番乗りする人間になるだろう・・・。
ハルとの対話 ディスカバリー号のシステムはすべて正常に機能していた。コントロールデッキからいつ遠心機にやってきたのかおぼえがない。気がついたときはキッチンのいすに座っていた、睡眠薬の永い眠りからさめたように、彼はゆっくり周囲を意識しはじめた。正面には魚眼レンズがあった、それはハル視覚入力装置で、船内の重要な場所には必ず配置されている。ボーマンははじめてそれを見るように見つめた。そしてゆっくりと立ち上がるとレンズに近づいた。突然ハルが離しかけた「困るんだろフランクがああなってしまったんでは?」「うん」長い間をおいてボーマンは答えた」この事件できみはかなりだげきを受けているね?」「何を聞きたいんだ?」この言葉を処理するのにハルは長い時間をかけた。・・・かれは優秀な乗員だった。ポッドのコントロール装置が故障して起こったのか?それともハルの故障(ミス)なのかハルに尋ねるきにはなれなかった。今でもフランクは故意に殺されたという考えを納得できないでいた。乗務員に一人が死んだときは生き残ったものは直ちに冬眠の一人を目覚めさせ補充しなければならない。冬眠カプセルをハルの管理下から引き離し独立した装置として冬眠装置を操作することも出来るのだ、今の状況にあってはそちらのほうが好ましい感じだった。「ハル」出きる限り平静な声で彼はいった。「手動コントロールをこっちにくれ・・・・全部だ!」全部だって「ボブ」「そうだ」補充は1人だということを忘れたのかい?」「非常事態が発生したんだ手助けはいくらでも欲しい、自分でやりたいんだ手動コントロールを渡してくれ」「デーブ」君には仕事が沢山あるじゃないか私に任してくれ」「ハル・・・・「手動冬眠に切り換えろ」「オー・ケーデーブ」とハルはいった。やがてボーマンの耳に聞きとれないほどの遠いモーターの音が聞こえてきた。
今までハルは絶対的な誠実さでその力と技能のすべてをたった1つの目的に投入してきた、故意の誤謬など考えられない。真実の隠蔽すら彼の心を不完全な誤りの意識でいっぱいにするものだった。人間でいえば罪悪感とでもいうのだろいうか。なぜなら彼もまたかれを創造した者たちと同様純真無垢の状態で生まれてきたからだ。彼はプールやボーマンに教えることの出来ない秘密について考えつづけていた。3人の冬眠者には冬眠に入る前に知らされていた、プールやボーマンは飛行のはじめの数週間、世界のテレビにひkkりなしに出演させられていたので、知る必要が起きるまで教えないほうがよいという策がとられていた。ハルにとっては自分の統合された意識をしだいに破壊していく抗争に気がついているだけだった。彼は間違いを犯すようになった、そして神経患者が自分自身の症状を客観的にみることが出来ないように、それを否定した。多くの人間が神経症の処理を自分でしているように、自分で何らかの処理をしていたかもしれない・・自分の存在を脅かす危機に直面しなかったら・・・・・・・ハルは接続を切ると、ボーマンに脅迫されたのである。ハルにとっては死に相当することだ、かれは自分の武器を総動員して自己防衛しようとした。誰にもじゃまされることなく任務を続行するつもりでいた・・たった一人で。 真空 ボーマンは近ずく竜巻のそれに似た轟音と風が体お引っ張り始めるのを感じた。空気が船から宇宙空間の真空へ噴出しているのだ。気圧が0に下がり意識を失うまであと10秒か15秒、考える余裕はなかった、だがそこで突然設計者の1人がかれにいったことを思い出した・・・事故を防ぐシステムはできるが、故意の事故を防ぐシステムまでは無理だ!。非常退避室の黄色い標識が見えた、よろめきながら近づき転がり込んだ、その小部屋は人1人と宇宙服が1着入るだけの大きさだった。その部屋には小型の酸素ボンベが備えてあった、ボーマンは最後の力をふりしぼって手元に引いた酸素が肺にに流れ込んできた、しばらく彼はあえぎながら立ちつくしていた。酸素の噴射が終わると突然静かさが戻ってきた、船内の大気はすべて宇宙に吐き出され船内は真空になったのだ。このまま宇宙服を着なくても一時間は生きていられるが無駄に酸素を浪費してしまうだけだ、宇宙服に入り外に出た。彼は事実を見定めるために冬眠カプセルに向かった、はじめにホワイトヘッドを調べた・次いで・カミンスキー、ハンターも・・・1目見るだけで充分だった。地球との通信も途絶えた宇宙船の中で彼は1人残されたのだ。ぐずぐずはしていられない打つ手は決まっている、やがて彼は楕円形のドアにたどり着いていた、その表面にはこんな表示が言葉が書かれていた「許可なき者は立ち入りを禁ず」「H19種許可書をお持ちですか」カギは無かったが、3枚の封印がドアを止めていた。ボーマンは前に1度だけ入ったことがある、まだ備えつけ工事が始まってまのない頃だった。無数のソリッドステート論理ユニットが上下に左右にずらりと並べられたその部屋は銀行の地下金庫室にどこか似たところがあった。ハルの目が彼の存在に反応したことはすぐにわかった、船内の送信機にスイッチがはいった・・やがて聞きなれた声が聞こえてきた「ハローデーブ」「生命維持装置に何か起こったようだね、デーブ」彼は気にとめなかった論理ユニットに注意深く目を通していた、これは、かなりきわどい手術になりそうだ、ハルの動力源を切るだけの話ではない、たとえそれが出来たとしても結果は破滅だろ、彼の管理がなければこ船は金属の屍となってしまう。この病んだ、だが才気溢れる頭脳の高等中枢だけを切断し純粋に自動的な管理システムだけはさせておく、それが唯一の解答だ。はじめるぞー彼は心のなかで言った。認識フィードバックとあるラベルのある区画を固定している棒をはずすと、彼は最初の記憶版を抜き取った。「おいデーブ」とハルが言った「何をしているんだ?」苦痛を感じるんだろうか?とボーマンの頭に浮かんだ。自我補強のラベルのある小ユニットを抜きとりはじめた、やがて部屋の中は中を行き交うユニットだらけになった。何重にも重複構造のおかげでコンピューターはまだ自我を保っている。今度は自動思考パネルにとりかかった。「デーブ」とハル「君はなぜ私にこんな事をするのかわからない、君は私の心を破壊しているのだ、子どもみたいになってしまう・・・存在しなくなってしまう・・・・」「わたしはHAL9000型コンピューター製造番号3号・・・わたしはイリノイ”・・3の逆数は0.33333333333333333333333333333333・・・・・・・・・・2*2わたしの最初の先生はチャンドラ博士$&”!デイジーデイジー・・彼は最後のユニットを引き抜いた、そしてハルは永遠に沈黙した。 秘密 フロイト博士はほとんど睡眠を取っていないように見えた。太陽系のはるかな端にいる孤独な男に、自信をうえつけようと彼は最善の努力を傾けていた。「HAL9000の故障の原因は我々のほうでもおよその見当がついている、それももう今となっては、緊急の問題ではないので説明はあとに回す、ここでこの任務本当の目的を話しておかなければならない」「2年前、我々は地球外知的生物の最初の証拠を発見した」TMA1とその周囲に群がる宇宙服を着た人々の写真がうつった、大変な事件だ・・・・だがそれと俺がどう関係あるのか?「物体のもっとも驚くべき特徴は、その古さだ地質学的に300万年前の物であることを立証した。その石板が月の夜が明けるとまもなく、太陽系中に非常に強力な電波エネルギーを放出した、それと同じ頃宇宙探査機の何台かがその異常な電波を検出、飛跡を辿ることが出来た、するとその方向にピッタリに土星があった。さまざまな事実を組み合せてみるとモノリスは太陽を引き金としたある種の信号機ではないかという結論がでた。300万年も進んだ生物の動機を何十もの理論で検討してみた結果、モノリスはある種の警報装置だろう、我々はその引き金を引いてしまった・・・、それを備えつけた生物が今も存在するかどうかわからない、したがって、君の任務は発見以上のものとなる、カミンスキー以下3人のチームはその任務の為特別な訓練を受けていた。しかし君は1人でそれを成し遂げなければならない、最後に君に目標を教える、土星面に進化した生物が存在するとは考えられない、今のところは目標を第八惑星・・・ヤスペタにしぼる。ヤスペタは太陽系の中でもユニークな天体だ直径800マイル月面望遠鏡でもやっと円盤がわかるくらい小さい、だがきわめて明るい、奇妙に対称的な斑点がその片面に見られそれがTMA1となんらかの関係をもっていると考えられる。これで君は本当の目的をしったわけだ。土星の衛星で君が出会うのは善なのか悪なのか・・・・それとも、トロヤの専売も古い廃墟なのか、それすらわかってないのだ。」 |
|
土星衛星群 |
|||
TMA1と土星系との繋がりに疑いを持つものはいない。だがモノリスを建造した生物がそこに発生したと信じる学者もまたいなかった。生命が存在する場所としては、土星は木星よりさらに条件が悪い。とすれば、はるかな昔地球を訪れた生物は、地球外ばかりか太陽系以外のものかもしれない。多くの科学者は、にべもなくその可能性を否定した。これまでに設計されたディスカバリー号でもアルファーケンタウリまで到達するのに二万年銀河系内でちょっとした距離を進もうとすれば数百万年はかかる。もし将来、推進システムが改良されたとしても、やがては越えることのできない光の壁にぶつかるだろう。どっちにせよ、知的生物がすべて人と同じように短命だと考えるのはおかしい。千年の旅でもちょっと退屈する程度という生物だって存在するかもしれない。「高速は本当に越えられない壁なのか?」なるほど、特殊相対性理論、もうじき百周年がめぐってくるぐらい耐久力を示したが、だが、そろそろ三つの割れ目が現れてきている。アインシュタインを否定することはできなくても、彼をさけて通れるかもしれない「地球外の知的生物はどんな形態をしているのだろうか?」二つの対立するグループによる一方は、類人生物に違いないと主張し、他方は、人間と似ても似つかぬ生物と信じて疑わないのだ。前者の論点は二足二手主要な感覚器官が身体の最高部についていることが、必然的かつ理にかなったもので、これ以上優れたデザインを考えるのは容易でないといい。別の生物学グループは、人体は永劫の年月に偶然が作り上げた何百万もの進化の選択結果であり、と彼らは指摘した。これとは別のもっと異様な考えかたをする者がいたことをボーマンは思い出した。真に進化した生物が肉体組織を持つとは、彼らは信じていなかった。科学が進歩するにつれ、やがて生物は肉体という棲かから逃れ出る、病気や事故からたえずつきまとわれ、死えとみちびく肉体などないほうがよいのだ。かれらは金属やプラスチックの製品に取替え不死性をかちとるのだ。脳髄は有機組織の最後の残存物としてしばらくとどまり、機械の四肢に命令を送るのだ。最後には脳髄さえ消えてゆくのだ。意識の着床する場所として電子知性になる。知性と機械との対立はやがて完全な永遠の妥協で終るだろう・・・・しかしそれが究極だろうか?そしてその先にまだ何かがあるとすれば、それは神以外にあるまい。
ビックブラザー 実 験 前 哨 眼のなかへ 退 場 |
| 星の門のかなた
|
グランドセントラル 動いている感覚は無かった。だが彼は衛星の奥深く輝く、信じられない星の海に向かって落下していた。ヤスペタのモノリスは空洞だったのかもしれない、屋上と見えたのは錯覚かもしれないし、あるいは何かの膜で、彼を通すために開いたのかもしれない(だが、どこへ連れて行くために?)五感を信じるとすれば、巨大な長方形のシャフトのなかを数千フィートの底へ向かって垂直に落下していった。はじめはゆっくりだったので、星が四角い枠の外に消えてゆくのに、なかなか気が付かなかった。だがしばらくすると、星の膨張がはっきりわかるようになった。まるでこっちに向かって想像を絶する速さで近づいてくるようだった。しかも星がなくなる様子はいっこうに無く、中心から無尽蔵に流れ出てくる。もしかしたら、じっさい彼は動いていず、空間が動いているのかもしれない・・・空間だけではないことに、彼は突然気がついた。ポッドの小さな計器パネルの上にある時計も、奇妙な動きかたをしていた。普通なら十分の一秒台の数字は目まぐるしく動いて目にも止まらないはずなのに、それが今でははっきり区別がつく間をおいて、動いていて読むことが出来るのだ。秒の桁は、時が停止するかと思えるようにゆっくりと動いていた。壁が動く速さは、0から高速の百万倍までどのあたりでのいいような気がした。なぜだか彼は少しも驚いていなかった、心配もしていなかった。前方の長方形が明るくなった、ポッドはトンネルから出かかっていた、突然正常な遠近の法則に従いはじめた。ヤスペタの中心まで下がり、反対側から出てきたのではないかと、つかのま思ったほどだ。しかしここがヤスペタとも、人間が知っている世界のどことも違っていることに気が付いていた。大気はない、信じられぬほど遠い、平坦な地平線の果てまで、あらゆるディーテルが、すみもせずみわたせることから、解った。ボーマンは、以前誰かから聞いた、南極の「ホワイトアウト」話を思い出した。同じ言葉はこの奇妙な世界でも通用する、ただ理由はまったく違う、気象学の理論で説明つくものではない。外部は完全な真空なのだから。やがてボーマンはべつのディーテルが目に入った、空一面に小さな無数の黒い点が動きもせず、無秩序に並んでいるのだ。白い空に見えるあの黒い点は、星なのだ。彼は銀河系のネガフィルムを見ているのかもしれなかった。宇宙全体が裏返しにされたという感じだった。彼は急に寒気を感じた、そして全身が、どうしょうないほど震えはじめた。そのとき、彼はふと気がついた、平原をおよそ二十マイル行ったあたりに、円筒形と見分けがつく金属の塊があるそれは巨大な宇宙船の残骸としか考えられなかった。この荒寥としたチエッカー盤にあの宇宙船が打ち捨てられたのは、何年昔のことだろう。そしてあれに乗って星の海を航海していたのは、どんな生物なのだろうか?・・・彼はすぐ残骸のことを忘れてしまった。何かが宇宙船上をこっちに、近づいてくるのに気が付いたからだ。はじめそれは円盤のように見えた、通り過ぎるころ、その長さは数百フィートの釣鐘形であることがわかった。その宇宙船は、地表にある何万もの巨大なスロットの、一つに向かって降下していくところだった。数秒後金色の船体を一瞬輝かせて惑星の深奥に消えた。その時、自分もまた、巨大世界のまだらの地表に向かって、ゆっくりと降下しているのに気が付いた。さっきのとは別の長方形の深淵がすぐ下にぽっかりと口を開けていた。それが太陽系の入り口でないことは、今では確信があった。その瞬間信じられない洞察が閃き、彼はシャフトの正体をつかんでいた。これは創造を絶する、時間と空間の次元を通じて、星間の交通をさばく宇宙転送装置に違いない。今彼通っているのは、銀河系のグランド・セントラル・ターミナルなのだ。 動いている感覚は無かった。だが彼は衛星の奥深く輝く、信じられない星の海に向かって落下していた。ヤスペタのモノリスは空洞だったのかもしれない、屋上と見えたのは錯覚かもしれないし、あるいは何かの膜で、彼を通すために開いたのかもしれない(だが、どこへ連れて行くために?)五感を信じるとすれば、巨大な長方形のシャフトのなかを数千フィートの底へ向かって垂直に落下していった。はじめはゆっくりだったので、星が四角い枠の外に消えてゆくのに、なかなか気が付かなかった。だがしばらくすると、星の膨張がはっきりわかるようになった。まるでこっちに向かって想像を絶する速さで近づいてくるようだった。しかも星がなくなる様子はいっこうに無く、中心から無尽蔵に流れ出てくる。もしかしたら、じっさい彼は動いていず、空間が動いているのかもしれない・・・空間だけではないことに、彼は突然気がついた。ポッドの小さな計器パネルの上にある時計も、奇妙な動きかたをしていた。普通なら十分の一秒台の数字は目まぐるしく動いて目にも止まらないはずなのに、それが今でははっきり区別がつく間をおいて、動いていて読むことが出来るのだ。秒の桁は、時が停止するかと思えるようにゆっくりと動いていた。壁が動く速さは、0から高速の百万倍までどのあたりでのいいような気がした。なぜだか彼は少しも驚いていなかった、心配もしていなかった。前方の長方形が明るくなった、ポッドはトンネルから出かかっていた、突然正常な遠近の法則に従いはじめた。ヤスペタの中心まで下がり、反対側から出てきたのではないかと、つかのま思ったほどだ。しかしここがヤスペタとも、人間が知っている世界のどことも違っていることに気が付いていた。大気はない、信じられぬほど遠い、平坦な地平線の果てまで、あらゆるディーテルが、すみもせずみわたせることから、解った。ボーマンは、以前誰かから聞いた、南極の「ホワイトアウト」話を思い出した。同じ言葉はこの奇妙な世界でも通用する、ただ理由はまったく違う、気象学の理論で説明つくものではない。外部は完全な真空なのだから。やがてボーマンはべつのディーテルが目に入った、空一面に小さな無数の黒い点が動きもせず、無秩序に並んでいるのだ。白い空に見えるあの黒い点は、星なのだ。彼は銀河系のネガフィルムを見ているのかもしれなかった。宇宙全体が裏返しにされたという感じだった。彼は急に寒気を感じた、そして全身が、どうしょうないほど震えはじめた。そのとき、彼はふと気がついた、平原をおよそ二十マイル行ったあたりに、円筒形と見分けがつく金属の塊があるそれは巨大な宇宙船の残骸としか考えられなかった。この荒寥としたチエッカー盤にあの宇宙船が打ち捨てられたのは、何年昔のことだろう。そしてあれに乗って星の海を航海していたのは、どんな生物なのだろうか?・・・彼はすぐ残骸のことを忘れてしまった。何かが宇宙船上をこっちに、近づいてくるのに気が付いたからだ。はじめそれは円盤のように見えた、通り過ぎるころ、その長さは数百フィートの釣鐘形であることがわかった。その宇宙船は、地表にある何万もの巨大なスロットの、一つに向かって降下していくところだった。数秒後金色の船体を一瞬輝かせて惑星の深奥に消えた。その時、自分もまた、巨大世界のまだらの地表に向かって、ゆっくりと降下しているのに気が付いた。さっきのとは別の長方形の深淵がすぐ下にぽっかりと口を開けていた。それが太陽系の入り口でないことは、今では確信があった。その瞬間信じられない洞察が閃き、彼はシャフトの正体をつかんでいた。これは創造を絶する、時間と空間の次元を通じて、星間の交通をさばく宇宙転送装置に違いない。今彼通っているのは、銀河系のグランド・セントラル・ターミナルなのだ。
見知らぬ空 地 獄 歓 侍 今では赤い太陽が空を隅々まで覆いつくしていた。上昇するガス下降するガスが渦を巻き、プロミネンス(紅火)天空に向かってゆっくりとふきあがっている動きが目に見えるのだ、時速百マイルくらいで、立ち上っているのに違いない。自分が進んでいく地獄のスケールをつかんでみたいとは思わなかった。ディスカバリー号が土星面と木星面を通過したとき、その世界の巨大さをいうあと言うほど思い知らされた。だがここでみる者は、その百倍も大きいのだ。眼下の火の海が大きくなれば、恐怖をおぼえるはずだった、だが妙なことに穏やかな不安しか感じなかった。自分がほとんどの全能の知性の保護のもとにあるのに、ちがいないことを論理で類推したからだ。これほど太陽に近づいたいま、なにかに保護されていないかぎり、瞬時に燃え尽きていりはずなのだ。スペースポッドは太陽面にほとんど平行なゆるやかな弧を描いて飛んでいたが、やがてゆっくり降下し始めた。その時はじめてボーマンは、音に気がついた。かすかな絶えまない咆哮、それがときおり紙を引き裂くような、あるいは、遠い雷鳴のような、バリバリという音で破られる。星のエネルギーは、まるでそれが別の宇宙に存在しているのかのように、彼を無視して暴れ狂っている。ポッドはその真っ直中を静かに進んでいるのだった。 デイビットボーマンは自分のために用意されているものを待ちうけた。眼下の地獄に偽りの夕闇が下りた、照明が変わった瞬間、周囲になにかが起こっているのに気がついた。流れる水をすかしてみているように赤色巨星の世界が揺らめいた。きわめて激しい衝撃はは通過したのかもしれない。スペースポッドは静まり返えった夜の中にうかんだ。一瞬の後、ほとんど感じられないほどの衝撃があり、ポッドは何かかたい表面に着陸し、停止した。「着陸?・・いったい何の上に・・?」ボーマンは信じられぬ気持ちで自問じとうした。やがて、光が戻った、不信感は、たちまち失意と絶望にとってかわった。なぜなら、周囲にあるものを見て自分の気が狂ったことがわかったからだ。地球の大都市なら何処にあってもおかしくない上級ホテル・ルームに着陸していた。目の前にはリビングルームがあり、コーヒー・テーブル・寝椅子など、さまざまなものがある。たとえ発狂しているにしても、幻想はみごとに構成されていた。すべてが現実そのものだった。この部屋はアメリカ合衆国の何処にでもあるホテルの部屋に似ている。だがそうだとしても、現実のここが、太陽系から何百光年も離れた場所であることにはかわりないのだ。彼はヘルメットの内部を機密した、そしてポッドのハッチハッチを作動させた。彼は部屋の床を踏んだ、完全なノーマルな重力だ。彼はホテルのルームへむかった、近づくにつれきえてしまうのではないかと思っていたが、それは現実のまま実態をもっていた。彼は電話番号帳をとりあげた、それには見慣れた活字のワシントンDCと印刷されていた。注意深く眺めてみると読める文字は、ワシントンCDという文字だけだった、ほかはぼやけて読めない、他のページは空白だで、紙によく似てはいるがあきらかに紙ではなかった。電話機を持ち上げダイアル音を聞いてみた、予想したとおおり何にも聞こえてこなかった。本や雑誌も同じで、三年前より新しいものは無く、知的な内容のものは皆無だった。好奇心ばかりではなく、空腹感にかられて、ボーマンはさがしはじめた。冷蔵庫を開けた、冷たい霧がふわりと吹きつけてきた。棚は缶詰でいっぱいだった、近くで見ると文字のラベルはぼやけていて読めない、バター肉の未加工品がまったくない。オートミールを開けてみた中には、湿り気をおびた青い物質が入っていた、奇妙な色をのぞけば、食欲をそそった。彼はベットルームに戻ると、ヘルメットと宇宙服をとると、急いでキッチンに戻り、例のオートミールを切れ割って慎重に臭いを嗅ぎ、二切れか三切れかみとると、よく噛みしめてのみこんだ。素晴らしい味だが、風味はどういっていいのかわからない。予期しない副作用でもでないかぎり、死の心配はこれでなくなった。すっかり満足したところで、飲み物をさがした、ビール見つけた、金具を押し開けた、ポンと開いた、ボーマン驚きと失望を感じた、これにもまた青い食品がつまっていたのだ。ほかの箱や缶を開けてみたが、ラベルが違っても内容は同じだ、食事はすこしばかり単調なものになりそうだ。元気を回復したところで手早くシャワーを浴びた、肌着、ガウンを身につけ、ベッドに身を投げ出し天井を見上げると、天井TVスクリーンがあった。電話や本と同じように、それも見かけではないかと、はじめは思っていた。めくらめっぽうにチャンネル・セレクターを回すと、アフリカのニュース、西部劇、フットボールの試合、東洋のパネルゲーム番組、ロシア語の番組、受信機調整用のマークなどを見た、それは世界のTV番組を片っ端から集めたもので、どの番組もTMA1が見つかった時期の、二年前の番組だった。今のところ知りたいことはすべて知ったので、TVを消した。これから何をしよう、彼は肉体的にも精神的にも疲れきっていた。こんな途方もない状況の中ででは、とても眠れそうもなかった。しかし気持ちのよいベッドと肉体にそなわった本能的な知恵が共謀し、彼の意志に逆らってはたらいた。明かりを消す、数秒もしない間に、彼は夢さえも届かない深い淵に沈んでいった。それがデビットボーマンの最後の眠りだった。 再 現 デイビット・ボーマンは、眠りの中で落ち着かなげに身じろぎした。何かが彼のなかに入りこんできた、彼はぼんやりとそれを感じただけだった。彼は宙に浮かんでいるようだった。小さな光の結節が、あるものはのろのろと、あるものは目もくらむ速さで動いていた。その光景あるいはまぼろしは、ひととき続いただけだった。やがて幾層も重なった透明な平面や椅子が行きかう結節は消え、ボーマンは人間がいまだかつて経験したことのない意識の領域に踏み込んだ、はじめは、時間が逆行しているように思えた。やがて彼はその奥に隠されている真相に気がついた。記憶の源泉が開け放たれていくのだ。彼は再び過去を生きはじめていた。赤い太陽の灼熱する表面、そして正常な宇宙に再突入したときに診た黒い出口、視覚ばかりではない、そのときの感覚、感情のすべてが速度を増しながらつぎつぎと通り過ぎていく。テープレコーダーのように、彼の人生が巻きほぐれていくのだ。かつて自分が愛した人々、もうすっかり思い出せなくなっていた人びとが、再びほほえみかけた。やがて逆行の速度がおとろえはじめた。停滞のちきが近づいていた、揺れる振り子が、次の位置に移る直前運動方向をかえた、地球から二万光年隔だった、二重星の真っ直中の、空っぽの部屋に赤ん坊が目を開き、うぶ声をあげた。 変 貌 星の子(スターチャイルド) |
| 倉田わたるの「2001年宇宙の旅」の真相 |
| 2001/08/06・記 2016/08/01・Renewal |

